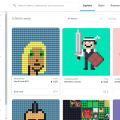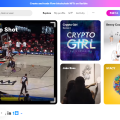鎌倉時代の東国武士たちは、中央の人事システムの埒外にあり、多くが無位無官で、出世やポストの誘惑で動くことは少なかったが、その代わり、「恩こそ主」を標榜した。現実に恩を受けている者のために働く、ということだ。

源頼朝が鎌倉幕府を創設する前は、平治の乱以降、「今そこにある恩」とは武家の棟梁であった平氏への恩であり頼朝にはその恩を使う効果はなかった。
そこで、頼朝が取ったのは、数のうえでの劣勢を、一人一人の「やる気」で補う戦略でした。1人をいわば10人分の戦力に仕立て上げる。そのために頼朝はどのような手を使ったのか。
それについて、『吾妻鏡』に印象的な記述があります。挙兵が間近い治承4(1180)年8月のこと。頼朝は、北条時政以下の家人を一人ずつ呼び寄せ、こう言ったといいます。
「いまだ口外せずといへども、ひとへに汝を恃む」
ようは「ここだけの話だが、お前だけが頼りだ」と囁いたのです。
これが「諸人の一揆」のための「方便」であろうことは、『吾妻鏡』の編者も冷静に指摘している。そして、「真実の密事」は北条時政にしか語らなかった、としています。
部下をやる気にする上司の「ここだけの話」
けれど、このときの「部下」の身になって考えれば、この頼朝の「囁き」作戦は効いたであろうと思われます。少なくとも、「昔は世話してやったじゃないか」などと言われるよりは、はるかに心を奮い立たせられたはず。
こうしたことは、今も昔も変わらず、現代の会社でも、上司の「ここだけの話」という「囁き」が、部下の士気を上げたり、プロジェクトを進める同志としての絆を強めたりしているのではないでしょか。
組織といっても、それを構成する一人一人の「心」が最終的には動かしています。多くの場合、人は打算で動いていますが、人間とは時に打算を超えた「心」で動く生き物です。それを動かしうるのが、よきリーダーや悪く言えば支配者の資質なのでしょう。
頼朝は、この「心」のつかみ方がうまかっく、また武士は、この「心」で動く部分が大きかったからこそ、頼朝は最終的に勝ったのでしょう。